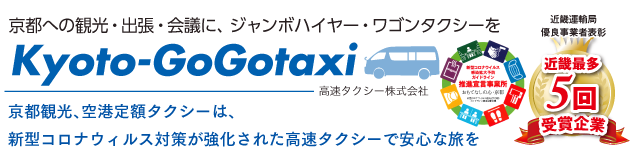丘は船岡 ~The mysterious zone~
休日に船岡山(ふなおかやま / 北区)へ。
単独登頂してきました笑

東端(写真ですと右端)が海に突き出した船のへさきに似てるところから名付けられました
歴史のある、そして京都を代表するミステリースポットです。
山は山なのですが標高112m、比高(※)40mの丘陵で、長い地質学の歴史においては
「京都盆地に置き忘れられた丘」
ということらしいです。 双ヶ丘、吉田山も同類です。
(※ある地域内の2地点間の高低差)
公園部分の管理は京都市で、山全体の所有は
「大徳寺」
であります。
なんとなんとです。 これも知らなかったです。
秀吉さんがこの山を大徳寺に寄進したそうです。
もう知らんことだらけ(^^;)
私事で恐縮ですが私はこの近くにある京都市立紫野(むらさきの)高校の出身です。
校歌の3番の出だしは
「深みどり 慕ひて登る 船岡の 哀しき歴史」
とあり高校に入った時点でこの山とは縁があるのです。
ですがココへは在学中に3回、その後も1回しか来たことがありません。
うち1回は高校の卒業アルバムのクラス写真撮影で。
たしか直前まで反対してました。
「もっと他にあるやろ。」と笑
登ったところで絶景が望めるわけでなし、昼なお暗くて特に何もないという観念しかなく、家族を誘った時なんかは反応すら無いといった有様でまったく足が向かなかったのです。
(家族の皆さんは薄気味悪いところとしか思ってません)
ということで私の「近くて遠いところ」 堂々の、断トツの、唯一無二の第1位となっています笑
(ちなみに自宅から徒歩10分)
とは言え、応仁の乱で「西陣」の拠点であったり、もっと遡れば清少納言に「丘は船岡」と言わしめ、王朝貴族の遊宴の地であったり、平安京造営時、朱雀大路(千本通り)の北の起点となったりと、さしづめ「歴史のデパート」のような場所で、一度くらいは敬意をはらっておくべきだと思い立ち一人でやってきたというわけです。

北側の入口 超久々にもかかわらず懐かしさを一切感じないのは? ミステリアスのはじまりです

今日はこのように周りました。ラフですみません

最初のアプローチはこんな感じです

頂上まで6分くらいでした。付近のマンションと比較したところせいぜい7、8階の高さかなと。比高40mはいったいどこを測ったのか?

向こうに見えるは「左大文字」 このまま走っていけそうです

西山連峰をのぞむ。 北野天満宮の杜が見えます
奥に京都タワー

この石段を上がると「建勲(たけいさお)神社」 (通称はけんくん) 織田信長公が祀られています。 ここは初めてです。

奥が本殿。御所に正対しています。 1869年、明治天皇の肝煎りでの創建

船岡山の東側にある鳥居 この前の道はけっこう通ってます笑
約30分かけて船岡山を周ってきました。
久々に訪れた(神社は初めて)感想は、
「どこまでも近くて、いつまでも遠い存在。」
近寄ったら、よけい離れていきました…
平安時代に王朝貴族が憩い戯れたこの場所が、朝廷の衰退とともに葬送の地や刑場として利用されだし、応仁の乱では多くの人々の血が流されたというダークな部分だけが残ってしまっているのです。
この山の1200年の歴史において最初に放たれたまぶしいばかりの光は、そのあと真っ黒な影を落としたまま、いつまでも消えることはないといったところでしょうか。
【今日の横道】 奥の細道?
以前、流しで紳士然とした男性が乗車され
「東京から京都が大好きでちょくちょく一人観光に来てるんです。」
「え?お一人でですか!?」
「はい、さっき船岡山へ行ってきました。すごくイイところですね。今日で2回目なんです。」
「え—っ!船岡山に?そりゃ珍しい!もう絶対京都通でいらっしゃいます。私そこの近くの高校…」
「あ、紫野高校ですね。たしか公立の進学校でサッカーの強い…」
「え!なんでそんなことまで知っておられるんですか! 船岡山よりスゴイやないですか!」
と、こちらが感動させられたことがありました。
タクシーではこんな不思議な出会いもあります。ミステリアスです。
船岡山はやはり京都の歴史にある程度精通した方が行くべき場所なんだろうと感じます。
まだ一度もという方はぜひ足を運んでみて下さい。
きっと歴史のロマン、息吹を感じることでしょう。
頂上まで行けば心地よい風が出迎えてくれるはずです。
幾星霜を吹きわたってきた千もの風が。
(どっかで聞いたような…)
私はまだ敬意をはらい足りてないのでもっと勉強してから再度トライします。
その時こそは幾星霜にわたり私の誘いを無視してきた家族を連れていきます。
掛見
(以前ネットか何かで「ここは●感の強い人が行けば『お祭り状態』だとスグにわかるところである」と書いてありました。私は肯定も否定もせず敬意をはらい続けます)